「上弦の鬼=病気説」はもう古い。妓夫太郎・堕姫が映す“人間の闇”と加害者心理
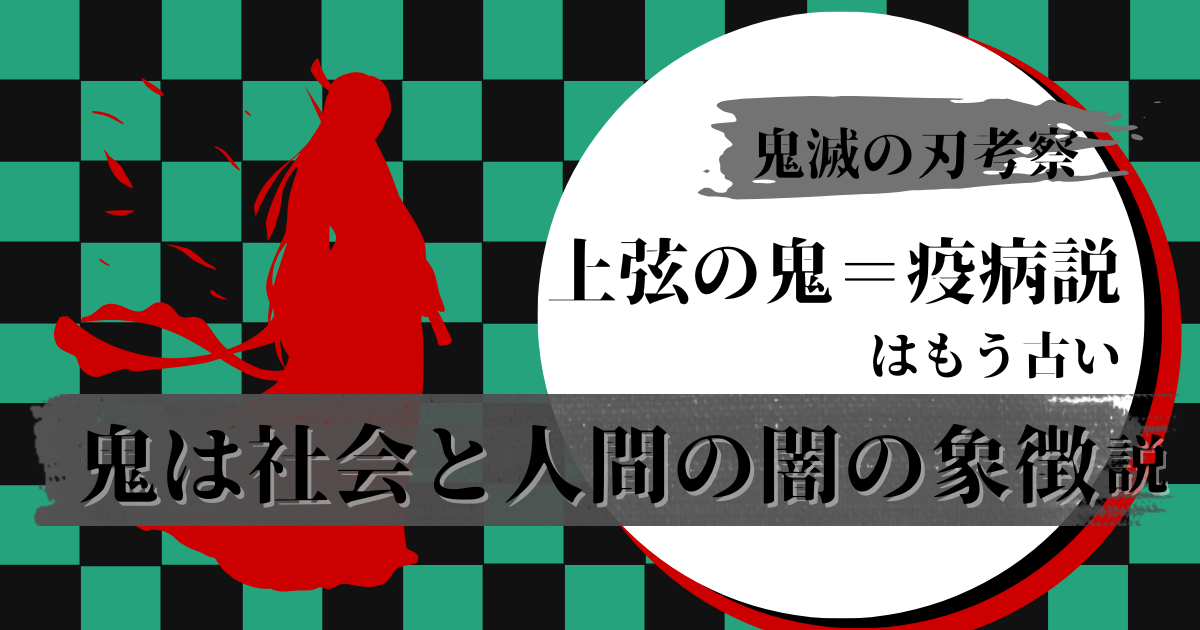

・鬼滅の刃 上弦の鬼のモチーフ考察に興味がある!という人。
・上弦の鬼=伝染病ってなんだか嘘くさくね?という人。
・鬼滅の刃のファンです!暇です!という人。
・優しい人。
※当ブログは考察系ブログとは無縁ですが、筆者あきたりょうが鬼滅の刃にハマりすぎた結果爆誕してしまったなんちゃってお茶濁し考察コンテンツです。「待ち合わせ時間になっても相手が来ない…」「病院や車屋の待ち時間が思ったより長い…」などのレベルで暇な方は読んでみてください。
※アニメを通り越して原作のネタバレを盛大に含んでおりますのでその界隈の方はご注意ください。
…はい、今更鬼滅の刃アニメを観てます。それにしても面白い作品です。そりゃぁその辺の小学生が傘持って「水の呼吸!」とかやってるわけです。私が小さい頃は「アバンストラッシュ!」でした。そして作画がすごい。最近のアニメって戦闘シーンの迫力がすごいですね。そりゃその辺の小学生が「炎の呼吸!」とやるわけです。ストラッシュ!
私が特に興味をそそられたのは「鬼」という存在でした。家族を、友人を、大切なものを理不尽に奪っていく存在。鬼滅の刃の世界観の中心ともいえる「鬼」とは、どこからやってきて何のために存在するのか?
調べてみると「鬼=病気・疫病・伝染病」という説があるようでした。読んでみるとふむふむなるほど次のように考察されているようです。
- 黒死牟=黒死病(ペスト) …名前似てるもんなぁ。歴史上最凶の伝染病とも言われていて黒死牟は上弦の壱。
- 童磨=結核 …血鬼術が結核の性質と似ている。
- 猗窩座=麻疹 …痣、赤い紋様が似て……似てるか?
- 半天狗=ハンセン病(らい病) …これは完全にアウトです
- 玉壺=アメーバ赤痢 …ア、アメーバ赤痢……?一応血鬼術が水や魚に関係ある。
- 妓夫太郎・堕姫=梅毒 …公式設定ではありませんが、堕姫の生前の名「梅」と妓夫太郎の生前の風貌がおそらく先天梅毒。
うーん、病気と直接の関連性がありそうなのは妓夫太郎・堕姫くらいかなと。それ以外はこじ付けか無理筋で、上弦の陸に関しても「梅毒そのものを象徴する鬼」ではないと思う。全体的に説に一貫性がないし、鬼たちの個性はもっと深いところにあると思う。こんなに濃く、魅力のある敵キャラクターたちなのだから。
そこでビギナーズノートの結論。上弦の鬼は「理解不能な加害者心理の象徴」説を推します。疫病や伝染病を象徴するのではなく、「負の感情がどこまで人を変質させるか」が上弦の鬼の裏テーマ。上弦の鬼(と無惨パイセン、おまけで鳴女と獪岳)ひとりひとりが、現代にも通じる「社会的恐怖」や「精神的異常」を象徴していると思うのです。
・黒死牟「競争社会での敗北による孤独」
・童磨「他人の痛みが分からないサイコパス」
・猗窩座「トラウマからくる衝動的な加害者心理」
・半天狗「極端な被害妄想、多重人格者」
・玉壺「屍体愛好、倫理なき芸術」
・妓夫太郎・堕姫「生まれの不公平、共依存」
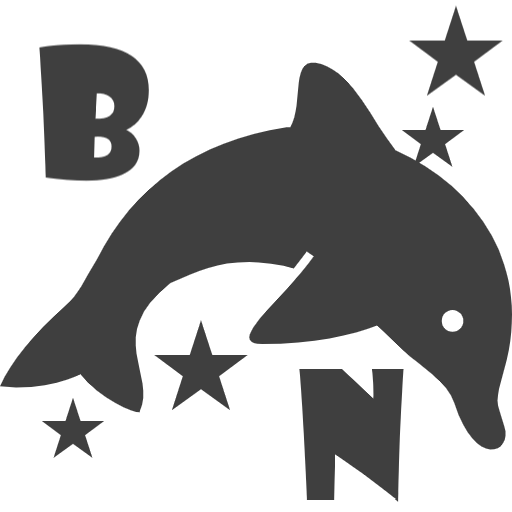
上弦の鬼のモチーフは「人間の闇」「理解不能な加害者心理」
疫病が全く無関係とも言えませんが、私が言いたいのは個性とドラマ溢れる鬼たちにはもっと深いところにその本質があるのではということです。
例として「BLEACH」の「十刃(エスパーダ)」を挙げてみる
BLEACHを読んだことがない人は、鬼滅の刃でいう上弦の月みたいなものだと思ってください。十刃それぞれが「人間が死に至る要因『死の形』」を司っており、
- 第1十刃 スターク「孤独」
- 第2十刃 バラガン「老い」
- 第3十刃 ハリベル「犠牲」
- 第4十刃 ウルキオラ「虚無」
(以下略)
例えば「老い」を司る第2十刃バラガンは見た目は怖そうなお爺ちゃん。能力を開放すると老い果てた骸骨に変身、そしてその能力は触れるものすべてを老い朽ち果てさせるというチート級の能力。司る言葉「老い」に対して一貫性がある。対する上弦の鬼は「疫病がモチーフ」としてしまうと「キャラクターへの一貫性」少し欠ける印象。

人間の闇、理解不能な加害者心理とは何か
人類はずっと昔から「死」「痛み」「疫病」「飢え」といった概念から遠ざかる努力してきました。しかしながら文明がどれだけ進化してきても、これらは人類が克服できない恐怖として君臨し続けています。それが鬼滅の刃、特に上弦の鬼たちが体現する概念ではないかと考えました。人類が克服できない恐怖はこれだけではありません。
例えば「競争社会での嫉妬」
人間は社会に溶け込み生活を営む性質上、ひとりでは生きていけない生き物です。だけど社会の中には否が応でも競争がある。「アイツに負けたくない」とがむしゃらに頑張って、気づいたら周りに誰もいない──自分自身も周囲に敬遠されるようなモンスターと化している。
敗者は存在意義を失って敗走し、勝者に残るのは孤独と虚しさ。どちらも報われない競争社会のなれの果て。この「報われなさ」と「孤独の苦しみ」は上弦の壱 黒死牟と重なります。彼は、嫉妬と競争の末、どれだけ強くなっても報われることはありませんでした。
「理解できないもの=怖い」という本能
人間は「わからないもの」「理解できないもの」を本能的に怖がります。上弦の鬼たちが見せる異常な心のかたちは、どれも現代社会に蔓延る“理解されないもの”に通じているように思います。
- 社会的貧困や差別、生まれの不公平(妓夫太郎・堕姫)※性病についてはむしろ描写が無い
- 「死や生命の終わり」を芸術に昇華させようとする“倫理を超えた創造欲”(玉壺)
- 自分以外がすべて敵に見えてしまう極端な被害妄想、多重人格の心理(半天狗)
- 普段は穏やかなのにちょっとしたことでスイッチが入ってしまうDV加害者のような心理(猗窩座)
- 人間らしい感情やそれに対する共感がない、何も感じられない人間の心理(童磨)
- 競争相手への強い嫉妬、どんな手を使ってでも勝とうとする執着心、その果て(黒死牟)
これらはどれも一般的に理解されにくく、それゆえ恐怖の対象とされてしまう人間心理、社会的心理です。
上弦の鬼たちは、こういった「理解不能で異常な心理」、簡単に言うと「人間の闇」を象徴しているのではないかと考えました。
それでは、個性豊かで魅力の溢れる鬼たちを具体的に見ていきましょう!
上弦の陸 妓夫太郎・堕姫 ── 貧困と搾取、兄妹の“共依存”
妓夫太郎・堕姫という鬼
『「妓夫太郎・堕姫」という鬼が生まれた経緯』を開く
- 生まれは遊郭の最下層。奪う・奪われるが日常の世界、常に「命の値段」が取引されている。
- 妓夫太郎の回想シーンで母親が梅毒であることがほのめかされており、生前の妓夫太郎もそれらしき痣や、ギザギザの歯など、先天梅毒である可能性がある。
- 生前の妓夫太郎はその醜さゆえに蔑まれ、口減らしに何度も殺されかけた。
- 妹の「梅」は兄とは対照的に絶世の美少女であり、実母は2人が幼いうちに逝去、父親は誰だったかも不明。生前の妓夫太郎にとっては、自分を慕い着いて回る泣き虫の妹が可愛くて仕方なかったという。その美貌ゆえ道を歩けば物をもらえ、うまく立ち回ることで飢えをもしのげるようになっていった。
- 「梅」は幼くして遊郭で金を稼ぐように。兄の妓夫太郎(生前の名はない)は腕っぷしの強さを使って妹への掛け金の取り立ての仕事をするように。
- 妓夫太郎の見た目の気味悪さから仕事はすこぶる上手くいき、「2人でならなんでもできる」と思った矢先に…
- 遊郭の女将(お店の店長のような人)にハメられ、妹はお客の侍によって生きたままに火炙りの刑に処されることとなり、激昂した妓夫太郎も侍への報復時に負傷、これが致命傷となり、死に至ると思われた所に…
- 当時の上弦の陸 童磨が現れる。童磨によって無惨の血を分け与えられ、2人揃って鬼となるのだった。
妓夫太郎・堕姫と「梅毒」との関係性(結論:象徴ではない)
生前の妓夫太郎が、胎児の段階で親から譲り受けた先天梅毒の可能性はある。さらに、彼が使用する武器、血鬼術には致死性の毒がある。これはおそらく梅毒とは直接の関係は無いが、「毒」という武器はそれを連想させる…という程度の関係性でしょう。毒で言えば玉壺も毒を使用することも整合性がありません。堕姫の方は、生前の名前が「梅」ってだけ。よって、まぁ、結論ほぼ関係ないと思います。性病の描写は無いし。っていうか少年漫画だし。
妓夫太郎・堕姫が象徴する闇 “壱” ──「生まれの不公平」と現代社会
妓夫太郎・堕姫はこの世に生まれ落ちた時点で「奪う以外に選択肢がなかった」境遇の持ち主でした。
遊郭の底辺という社会では、努力や才能よりも「美しさ」か「ケンカの強さ」、そして「運」があるかが生死に直結する世界観です。妓夫太郎は醜さゆえ暴力しか選べず、「梅」は美しさゆえに身売りしか選ぶことができなかった。遊郭の底辺に生まれてしまった時点で、彼らは「生まれの不公平」という理不尽の泥沼にズブズブだったわけです。この構図は、現代社会でも全く珍しいものではないと思います。
見た目や家庭環境、経済格差。近年では「親ガチャ」なんて言葉も流行っていますが、そんな「生まれのくじ運」で人生が左右される世界は確かに存在します。妓夫太郎・堕姫はそんな世の中の不条理を象徴しているのではないかと思いました。
妓夫太郎・堕姫が象徴する闇 “弐” ──「絆」ではなく「共依存」
妓夫太郎と堕姫は、どこまでもお互いを想い合う兄妹でした。兄に付いて回り、離れれば泣き喚く妹がこの上なく愛おしいと感じていた生前の妓夫太郎。「梅」も生まれながらにして過酷な毎日を助け合ってきた過去から兄を誰よりも頼りにしていました。「梅」にとっては他に頼れる人がいなかったのは事実かもしれませんが、いずれ兄妹の絆自体は本物だったのでしょう。
きっと、どんなに醜い生き方であろうとも「兄妹で一緒ならそれで良い」と心から思っていたことでしょう。その純粋さが同時に、彼らにとって最大の悲劇でもあったのかもしれません。
「梅」は兄に守られることで生きてきた。兄を誰よりも頼りにしていた。
兄・妓夫太郎は、妹を守ることでしか自分の存在価値を見出せなかった。
2人の「絆」の裏には、世にも美しい「共依存」が成り立っていたのでした。
もし生前の「梅」が兄の影から離れて生きる力を持てていたら──
もし生前の妓夫太郎が妹への執着を少しでも手放せていたら──
妓夫太郎の死に間際には、素直で染まりやすい性格の「梅」なら、良家に生まれていれば、あるいは良家に身請けされていたならば、客の侍に従順にしていたならば、違った人生があったのではないか、自分といたせいで鬼になる道を歩ませてしまったのではないか、それが唯一の心残りだ……というワンシーンもありました。
でも、それができなかった、愛ゆえにお互いに依存することしか選べなかったのが、彼らの「人間らしさ」だったのだと思います。
炭治郎は妹を守ることで強くなった。
妓夫太郎は妹を守ることで壊れていった。
同じ兄妹愛の、同じ兄妹の絆のはずなのに、そこにあるのは光と闇のような対照性。
竈門兄妹との対比があまりに悲劇的です。
心理学からひも解く妓夫太郎・堕姫の共依存
心理学における「共依存(codependency)」とは、他者の存在を通してしか自分の価値を確認できない関係を指します。愛情や絆のように見えても、その実態は「相手がいなければ自分が成り立たない」状態です。
妓夫太郎と堕姫の関係は、この共依存構造の典型例として見ることができます。
妓夫太郎は「妹を守る自分」であることが存在意義であり、
堕姫は「兄に愛される自分」であることで安心を得ていました。
このように、相互に依存することでしかアイデンティティを保てない関係は、一見すると深い愛情のように見えて、実は互いを束縛し合う危うさを内包しています。
また、共依存関係の根底には「自己評価の低さ」と「過去のトラウマ」が存在します。
妓夫太郎は“醜い自分”を世界が否定する中で、唯一無条件に慕ってくれる妹の存在に救われていました。
堕姫は“過酷な世界”の中で、兄が唯一の安全基地でした。
互いに「他に頼れる人がいない」という環境が、この依存構造をより強固にしたと言えます。
心理学的に見ると、共依存は「愛の形」ではなく「自己喪失の結果」として現れます。
妓夫太郎も堕姫も、自分自身を確立する前に「相手を守る・求める」ことで生き延びてきた。
そのため、どちらかが崩れればもう一方も共に壊れる──
まさに、兄妹という枠を超えた“共倒れの絆”だったのです。
現代社会でも、恋人関係や親子関係など、似たような共依存構造は少なくありません。
「守る」「助ける」といった行動が、いつの間にか「支配」や「自己犠牲」にすり替わる。
妓夫太郎と堕姫の関係は、そんな「共依存」の心理的メカニズムを象徴していると考えられます。
まとめ:妓夫太郎・堕姫は「生まれの不平等」と「共依存」の象徴
今回の記事では妓夫太郎・堕姫の生前の境遇、生まれながらにして奪う以外の選択肢が無かった「生まれの不平等」と、「共依存」という歪んだ兄妹愛を紐づけて考察してみました。
もちろん他にもたくさんの解釈があってこそストーリーを最大限に楽しめると思いますので、「ふーんそういう考え方もあるのね」程度に考えてもらえれば嬉しいです。
次回!にょろにょろキモカワ玉壺たんとワシは悪くないじいさん半天狗の考察回もぜひお楽しみに!!
鬼滅の刃考察 最新記事はこちら👇
上弦の参・猗窩座の加害者心理を犯罪学と社会構造から考察。病気説を否定し、…
※当ブログは考察系ブログとは無縁ですが、筆者あきたりょうが鬼滅の刃にハマ…
※当ブログは考察系ブログとは無縁ですが、筆者あきたりょうが鬼滅の刃にハマ…
※当ブログは考察系ブログとは無縁ですが、筆者あきたりょうが鬼滅の刃にハマ…
考察のようなものはSNSでも呟いてます👇
鬼滅の刃考察ビギナーズノート
『鬼滅の刃』の考察を楽しむだけに作ったアカウント
ポストや記事は個人の意見なので公式とは無関係🙅♂️
人の数だけ解釈があって良い派なので、異論は歓迎ですが議論はしません🕊
共感して頂けたらコメントを頂けると励みになります😌✨


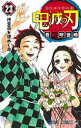

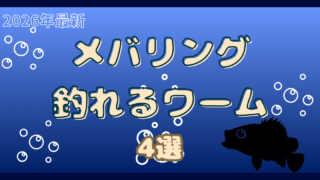
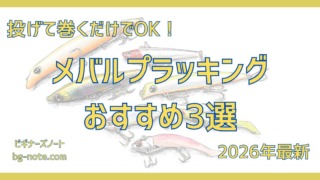
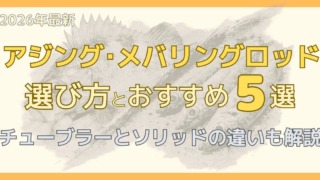

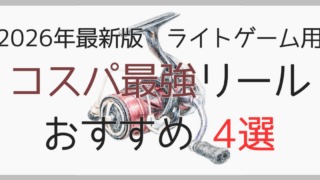

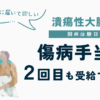
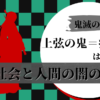
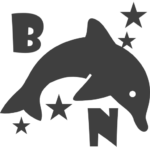



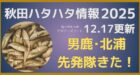

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません