UC闘病体験日記|コレチメント(ブデソニド)中止の理由と潰瘍性大腸炎
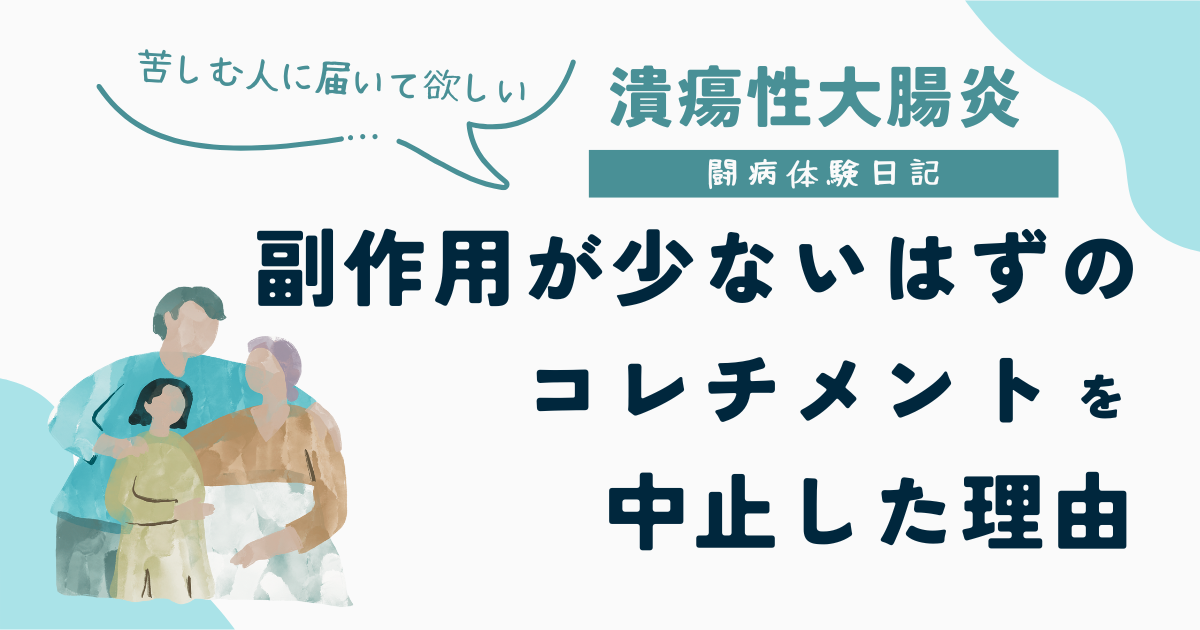

2020年に潰瘍性大腸炎(左側炎症型 中等症)を発症。全身性ステロイド「プレドニゾロン」を服用しながら約5年間寛解。再燃後、副作用の少ない新薬「コレチメント(ブデソニド)」で仕事と家庭を両立しながら、治療を継続。ゆるやかに寛解に向かっている感覚がありましたが、6週目あたりで発熱、血便・下痢の増加など異変を感じ、主治医の元へ駆け込みました。
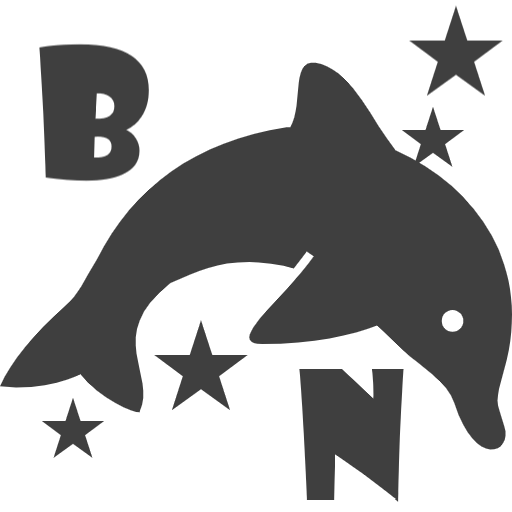
UC闘病体験日記シリーズ最新記事はこちらからどうぞ
. 潰瘍性大腸炎と食欲不振・体重低下の関係 潰瘍性大腸炎が再燃(発症)し…
. . 通院ごとに行われる血液検査の結果 潰瘍性大腸炎(UC)では、通院…
コレチメント(ブデソニド)の特徴を再確認
ステロイド依存型の潰瘍性大腸炎を治療する筆者が2025年1月から服用した「コレチメント(ブデソニド)」の特徴を再確認していきたいと思います。
コレチメントはどんな薬?改めて特徴を整理
まずは、治療の主軸となる薬剤「コレチメント(一般名:ブデソニド)」について、改めてその特徴を整理しておきます。コレチメントは「潰瘍性大腸炎(UC)」の治療を念頭においた局所作用型のローカルステロイド(大腸に対して局所的に効果を発揮する)で、2023年6月と比較的最近認可された新薬です。
これは、従来の全身性ステロイド(プレドニゾロンなど)に比べて以下のようなメリットが期待されています。
- 経口摂取後、大腸に到達してからその成分を放出するように設計されている。
- 血中に移行するステロイド濃度の上昇が比較的抑えられるため、副作用リスクが大幅に軽減されている。
- 炎症性サイトカイン(TNF-α、IL-1βなど)を抑制し、腸粘膜の炎症を鎮める作用がある。
このような特徴により炎症をピンポイントで抑えることで「効果」と「安全性(副作用のミニマム化)」を高いレベルで両立する潰瘍性大腸炎(UC)の治療薬として期待されています。
全身性ステロイドとの違いと安心感の理由
従来、潰瘍性大腸炎(UC)の治療には全身性ステロイド(例:プレドニゾロン)が使われることが多く、その即効性は非常に魅力的ですが、全身に作用するがゆえ次のような懸念もつきまといます。
- ムーンフェイス、食欲増進、体重増加
- 免疫低下、感染症リスクの上昇
- 骨粗しょう症、糖尿病、高血圧の悪化リスク
- 不眠、情緒不安定など
一方で、コレチメント(ブデソニド)は局所作用型ステロイドという性質上、血中へのステロイド移行が抑えられ、上記のような全身性の副作用をある程度抑制されることが期待されます。私自身、服用中はプレドニゾロン服用時とは副作用の出方が非常に緩やかなのを実感していました。(というか、生活に支障をきたすレベルの副作用は感じませんでした)
| 副作用項目 | プレドニゾロン(全身性ステロイド) | コレチメント(ブデソニド) |
| 不眠・情緒不安定 | 多くの人に発現 | ほとんどない~軽度 |
| 食欲増進・体重増加 | 多くの人に発現 | ほとんどない~軽度 |
| ムーンフェイス(顔の腫れ) | やや高頻度 | 稀に発現 |
| 肌荒れ・ニキビ | 多くの人に発現 | ほとんどない~軽度 |
| 免疫低下による感染症 | 常に注意が必要 | 少し注意した方が良い |
| 胃の不快感 | やや高頻度 | ほとんどない~軽度 |
| 効果の現れ方 | 早い、即効性がある | ゆるやか(1~2週間) |
ただし、「副作用が完全になくなる」わけではなく、あくまで「軽くなる可能性が高い」という理解が正しいでしょう。薬剤選択の際には、既往歴や感染症リスクの評価も重要になります(事項で触れます)。
コレチメント投与前に必ず確認すべきウイルスキャリア・既往歴
※「必ず確認すべき」と表現しましたが、実際は病院での検査が必ず行われます。
潰瘍性大腸炎(UC)のように、免疫・炎症制御が治療のカギとなる疾患において、ステロイドあるいは免疫抑制を伴う治療薬を用いる前には、患者さんそれぞれの既往歴・ウイルスキャリアの有無を慎重に確認することが非常に重要です。具体的には以下のようなチェックが一般的に行われます。
- 血液検査:ウイルス抗体、ウイルスDNAの検査
- 問診等による既往歴の確認:肝炎、帯状疱疹、そのほかのウイルス感染症など
- 合併症、並行服用薬の確認:腎機能障害、肝機能低下、糖尿病などを既往していないかどうか
「○○があると、ステロイド治療はできない!」という○○の要素をあらかじめ洗い出しをしてから、服用が開始されるのが一般的であり、重篤な副作用を未然に防ぐためには必須のチェックになるということですね。
私の場合は、「潰瘍性大腸炎(UC)以外に大きな病気はしたことがなかった」ので、問診でもそう答え、お薬手帳も確認してもらい、その上でのステロイド治療を約5年続けていたはずでした。
前倒し入院で、大腸カメラで腸内を確認してみると、炎症は左側に留まらず大腸全体に広がっている。後日、主治医によるとサイトメガロウイルスの再活性と思わしき炎症痕、炎症があるとのこと。だ、だれですねん、あなた……ともかく、急な高熱、下痢・血便の増加、頻回化はコイツ(サイトメガロウイルス)もUCと同時進行で悪さをしているということで、ステロイド治療を断念する判断を下すこととなりました。
コレチメント服用6週目から感じた異変
時系列を少し戻しまして、入院し大腸カメラ検査をする前まで戻ります。コレチメント服用から1か月頃はゆるやかに体調が回復している感覚がありましたが、6週目を過ぎるあたりで体調不良を感じ始めました。
ゆるやかな回復から一転 ──急な高熱と下痢・血便の増加
服用を開始してからおよそ1か月半。体調はゆるやかに回復傾向にありました。腹痛はグンと減り、下痢・血便の頻度も減少、仕事や家庭のリズムも戻りつつあった、その矢先のことでした。
コレチメント服用6週目あたりから明らかな体調の変化がありました。体温は初動で39.6℃まで上昇、次の日からは38.0~38.5℃をさまようことに。締め付けられるような腹痛、頻回の泥状便と結構な量の血便。誰がどう見ても「潰瘍性大腸炎の再燃」でした。
初めは風邪っぽかったので、風邪が重症化して、潰瘍性大腸炎(UC)も一時的に再活性したのかなと思っていました。ドカッと熱が出ることも今までも普通にありましたので、熱が出た直後は解熱剤を飲んで安静にしていればまたゆるやかに体調は回復するだろうと静養に努めました。コレチメント服用はそのまま続けました(自己判断でのステロイド中断が一番危ない)。
7週経過、腹痛と貧血が限界。診断日を前倒して、そのまま入院。
※この辺の時系列はこの辺です。妻に「治るまで帰ってくるな!」と追い出され、妻のおかげで万全の態勢で入院できました。
7週目を迎える頃には明確に症状が悪化し、便の回数は1日10回を越え、熱は解熱剤を飲んでも37℃を下回らない。血便の量も明らかに増え、貧血で立っていられませんでした。当然、体力は急激に落ち込み、仕事も家庭も手が付けられない状態に。限界でした。
診断予約日を前倒しにして、血液検査を経て診察室へ入り、体調と就労不能なことを伝え、入院を受け入れてもらえました。文字通り治療に専念することになりました。その日のうちから絶食、翌日には大腸カメラを手配してもらえました。
大腸カメラ検査で見えた新たな炎症
…といっても、この時の大腸カメラ検査は腸粘膜が荒れに荒れていたことで痛すぎて顔は歪み、リアルタイムではほとんど自分の大腸粘膜を見られませんでした。翌日担当して頂いた看護師さんに自分の大腸粘膜の様子が見たいとお願いして、記録画像を見せてもらいました。
これまでにないレベルの粘膜びらん
入院直後に行われた大腸カメラ検査では、想像以上に大腸粘膜が荒れていることがわかりました。
これまでの炎症は左側(直腸付近からS状結腸あたり)が中心でしたが、今回は右側結腸まで広範囲に炎症が及んでいたのです。
検査中は、内視鏡を操作する検査担当の先生も、「これは痛いでしょうね、頑張って……」とおっしゃってました。優しい先生だったなぁ……いでーーーー!!!って叫んでいたので、検査後、入り口の看護師さんにもとっても心配されました。痛かったんだよ。
診断結果──サイトメガロウイルス再活性の疑い
検査の結果、腸粘膜から採取した組織検査でサイトメガロウイルス(CMV)感染の反応が見られました。コレチメント(ブデソニド)をはじめとしたステロイド治療による免疫抑制がウイルスの再活性を誘発した可能性があるとのことです。
サイトメガロウイルス(CMV)は多くの人の体内に潜伏しているウイルスで、通常は免疫が正常に働いている限り問題を起こさないザコウイルスなんだそう。しかし、ステロイド治療などで免疫抑制、つまり免疫を意図的に下げる治療をしていると顕現して再活性することがあるんだそうです。その顕現率は約20~30%、そんなにあり得なくもないという数値ですね。
このサイトメガロウイルス(CMV)が再活性したことで潰瘍性大腸炎(UC)に由来する炎症も誘発するようにして活性化してしまい、結果、私の身体にはコレチメント(ブデソニド)は合わなかったという苦渋の判断を下したことになりました。
なんで今更サイトメガロウイルス(CMV)が再活性??
純粋に疑問なのはなぜプレドニゾロンの時はサイトメガロウイルス(CMV)が出てこなかったのか?先生も「複合的な理由があって、理由の特定は難しい」とおっしゃってました。
コレチメント(ブデソニド)は副作用の少ない大腸局所性ステロイドだから、大腸の免疫だけを狙って下げた。そしたら大腸にもともと居たウイルスが活性化した。ということなのだろうか?
先生の言う通り、複合的な理由があって分からないというのが結論なものの、副作用の少ない薬で寛解を迎えられなかったのは、自身が不運だったことを認めざるを得ませんね。次の治療を頑張ろう!
コレチメント(ブデソニド)中止、次の治療方針へ
こうした検査結果を受け、コレチメント(ブデソニド)の継続は中止されました。主治医と相談の上、今後はJAK阻害薬「ジセレカ(一般名フィルゴチニブマレイン酸塩またはフィルゴチニブ)」へ切り替える方針となりました。
コレチメント(ブデソニド)は確かに副作用が少ない優れた薬ですが、免疫を意図的に下げることにより、思いがけない潜伏ウイルスの再活性が起こる可能性があります。「全身性ではない=安全」とは簡単にはいかないことを思い知らされた結果となりました。
継続的な投薬などで治療を続ける場合は、「その薬が自分に合っているかどうか」を見極める気持ちで、継続的に自身の体調を観察することがとても重要だと、改めて感じることになりました。
次回はJAK阻害薬「ジセレカ」について少し勉強して、途中経過の報告ぐらいまでを頑張ってまとめてみたいと思います。
以下、参考にさせて頂きました
参考文献
- コレチメント®錠9mg 添付文書(持田製薬株式会社/RAD-AR 医薬品リスク管理総合機構)
- 持田製薬「コレチメント®」製品情報ページ
- 厚生労働省 医薬品評価関連資料|ブデソニド(Budesonide)体内動態・安全性情報
- 国立成育医療研究センター|潰瘍性大腸炎(UC)の治療指針・薬物療法
- QLife 医療用医薬品情報|ブデソニドの薬理作用・副作用一覧
日本消化器病学会「潰瘍性大腸炎診療ガイドライン2023」
日本消化器病学会, 南江堂, 2023年改訂版 - 厚生労働科学研究班:潰瘍性大腸炎におけるサイトメガロウイルス再活性化の実態調査報告(2022)
- PubMed: “Reactivation of cytomegalovirus infection in patients with ulcerative colitis under corticosteroid therapy” (J Gastroenterol Hepatol. 2018)
SNSもよろしくお願いします!
あきたりょう|1歳娘のポンコツ父ちゃん×潰瘍性大腸炎
1歳娘のポンコツ父ちゃん👶🔰|ENTJ-A|塾講師歴10年📚今は普通の会社員|💊潰瘍性大腸炎(全大腸炎型中等症)|海釣りキャンプDIY|📖blog闘病体験日記や趣味のこと、教育のことを備忘録として書いてます|無言フォロー、突然のコメントご容赦下さい🙇
UC闘病体験日記の最新記事はこちら
. 潰瘍性大腸炎と食欲不振・体重低下の関係 潰瘍性大腸炎が再燃(発症)し…
. . 通院ごとに行われる血液検査の結果 潰瘍性大腸炎(UC)では、通院…
UC闘病体験日記シリーズ最新記事はこちらからどうぞ ステラーラはどんな薬…
UC闘病体験日記シリーズ最新記事はこちらからどうぞ . JAK阻害薬「ジ…
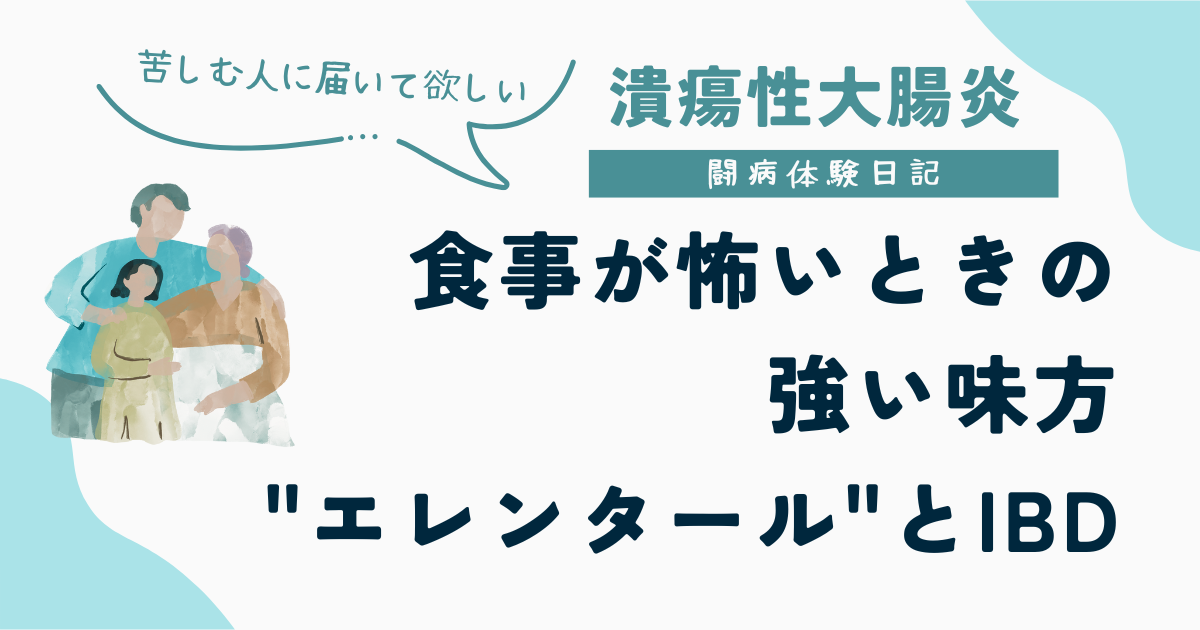
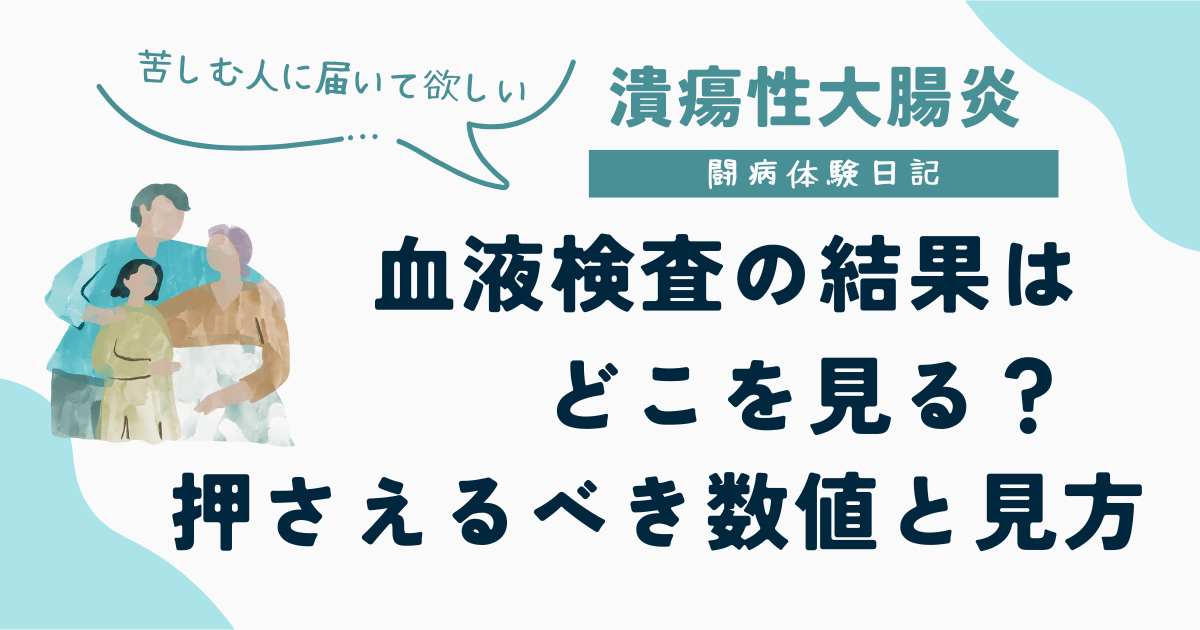

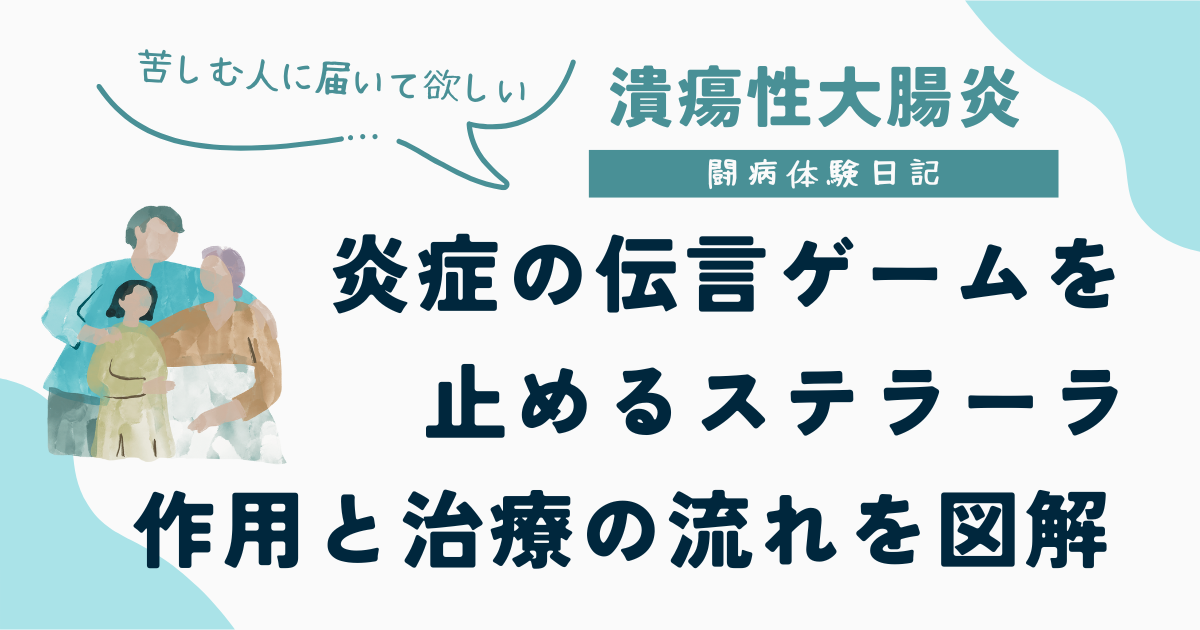
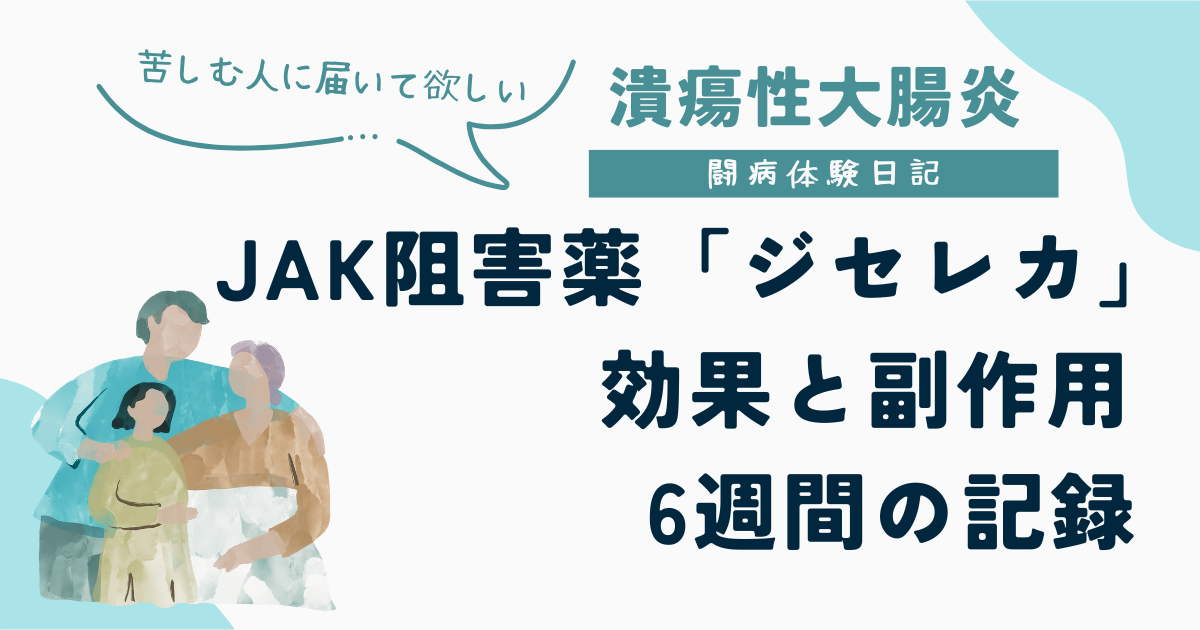
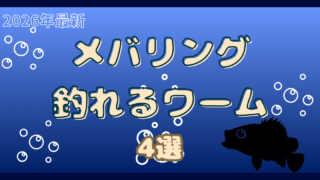
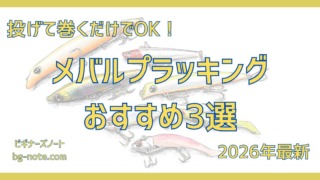
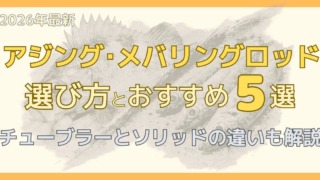

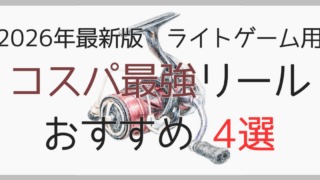


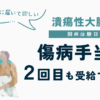


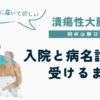

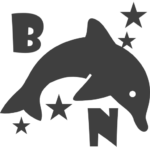


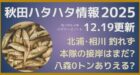


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません