薬の飲み忘れ防止策3選|スマホ・ピルケース・紙でできる簡単対策とNG例
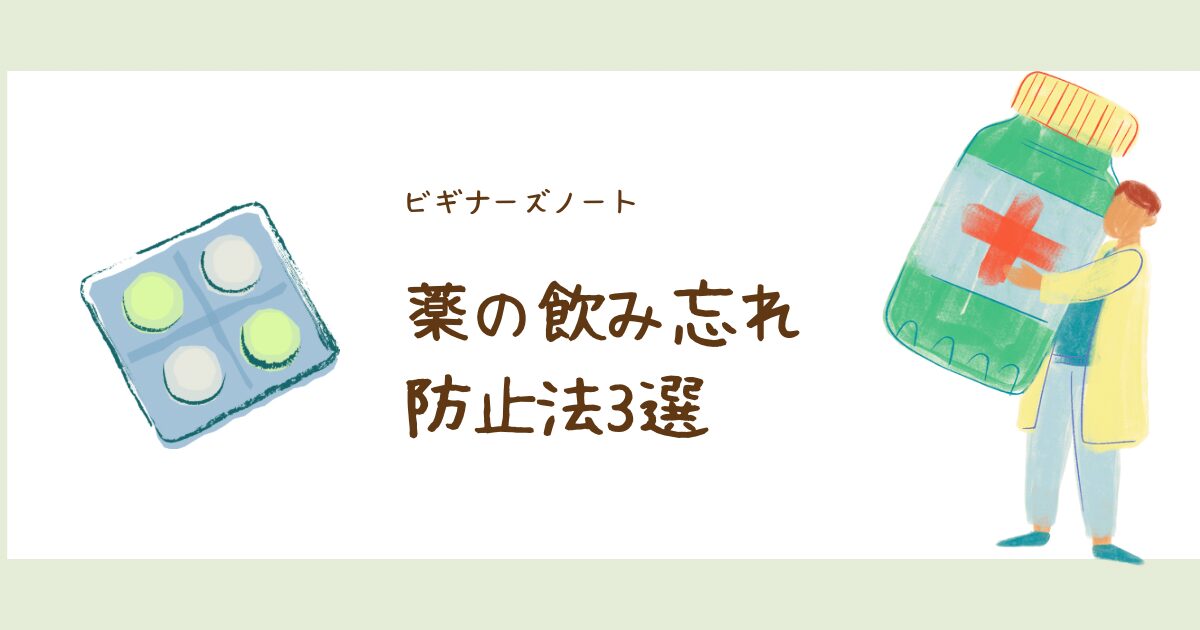

・毎日薬を飲んでいるが、つい飲み忘れてしまうことがある
・薬の飲み忘れを防ぐための便利な方法や対策を知りたい
・忘れずに薬を飲むコツや習慣化の工夫を探している
・家族や子どもの薬の服薬管理に悩んでいる
大変失礼なお話ですが、薬の飲み忘れなどご高齢の方に限った話だと愉快な勘違いをしておりました。私自身毎日薬を飲む必要があるのですが、「あれっ、今日薬飲んだっけ…」と自身がなくなることが多々ありました。
本記事では、毎日服用が必要な薬を忘れずに飲むための工夫を3つご紹介します。また、よくありがちだけどあまりおすすめできない方法も併せて解説します。
方法1:スマートフォンのリマインダー機能を活用する
もっとも手軽で確実な方法は、スマートフォンの「リマインダー」や「アラーム機能」を使うことです。毎日決まった時間に薬を飲んでいる人なら、スマホから通知が来るだけで飲み忘れを防げます。
とくに、服薬に特化したリマインダーアプリを使うとさらに便利です。代表的なアプリには以下のようなものがあります。
これらのアプリでは、通知だけでなく、薬の記録や服用履歴を可視化する機能もあります。「飲んだつもり」「まだ飲んでないかも?」といった曖昧な記憶を防ぎ、正確な服薬管理が可能になります。
方法2:ピルケース、ウォールポケットに薬を保管する
毎日複数の薬を服用する必要がある方にとって、視覚的に薬の有無を確認できる仕組みは非常に有効です。中でも「ピルケース」や「ウォールポケット」は、飲み忘れを防止する手段として根強い人気があります。
ピルケースは1週間分を朝・昼・夕など時間帯別に分けて収納できるタイプや、1日1回の服用向けのシンプルなケースなど、ニーズに合わせて様々なタイプが販売されています。飲んだかどうかを目で見て確認できるので、飲み忘れや重複服用の予防にも効果的です。
また、薬を飲んだかどうかを視覚的に確認できるため、服用者を支援する人にとっても管理、支援がしやすいです。
ポイントは、服薬を「行動の一部」に組み込むこと。たとえば、朝食後すぐにピルケースの薬を取り出す、寝る前にウォールポケットを確認するなど、「〇〇をしたら薬を飲む」という生活の流れに組み込むことで、習慣化がしやすくなります。
デメリットとしては、持ち運びにはやや不向きであることや、分割する作業が手間に感じられる場合があることです。しかし、日常の中で「目で見て管理したい」方にとっては、非常に効果的な方法です。
方法3:紙媒体に記録する
スマートフォンの操作が苦手な方や、デジタルに頼らずアナログで服薬管理したい方には、「紙での記録」もおすすめの方法です。カレンダーやチェックリスト、手書きの薬の記録表を活用することで、薬を飲んだかどうかを毎日確認できます。
たとえば、冷蔵庫や机に貼ったカレンダーに「✓(チェック)」を入れるだけでも、記録と習慣化の両方を促せます。手帳に簡単な記録を書く方法も、意外と効果があります。朝・昼・夜の欄を作ってチェックするだけでOKです。
この方法の最大のメリットは、柔軟性と記録の残りやすさ。紙は電源が不要で、誰にでも簡単に扱えるため、世代を問わず実践できます。また、通院時に医師へ服薬状況を説明する際にも、紙の記録は役立ちます。
ただし、注意点もあります。紙の記録は自分で「記録することを忘れてしまう」と、結果的に飲み忘れにつながってしまう可能性があります。そのため、紙のチェック表や服薬記録は冷蔵庫に貼る、ダイニングテーブルに置く、洗面所に貼るなど、日常生活の中で必ず目に入る場所に設置する工夫が効果的です。
また、薬を飲むタイミングとセットでチェックするよう習慣づけることで、「記録をつける習慣」そのものが服薬管理の一部になります。紙はあくまでも補助ツールであることを意識し、視覚的な仕掛けと組み合わせて活用するのが成功のポイントです。
おすすめしない方法:手書きのメモや「覚えておく」だけに頼る
服薬を習慣化できていない段階でよくあるのが、「今日は◯時に飲む」と自分の記憶だけに頼ったり、紙のメモ帳に予定を書くだけで済ませる方法です。しかし、これらの方法は飲み忘れのリスクが非常に高く、基本的にはおすすめできません。
手書きのメモは、一度書いた後に見返さないまま忘れてしまうことが多く、置き場所によってはすぐに目につかないことも。スマートフォンのように通知機能があるわけでもないため、視覚的・聴覚的なリマインドが働きにくいのが難点です。
また、「頭の中で覚えておく」という方法は、忙しい日常生活の中では特に忘れやすくなります。服薬の習慣がまだ身についていない時期にこそ、記憶に頼らず、仕組みに頼ることが大切です。
どうしてもメモで管理したい場合は、目に入る場所に貼る、他の方法と併用するなどの対策を講じたうえで使用することをおすすめします。
まとめ:あなたに合った“仕組み”を作ろう
薬の飲み忘れは、体調や病状の悪化に直結する場合があります。「気をつけよう」とするだけでは限界があるため、自分に合った仕組みを取り入れることが何より重要です。
どれも少しの工夫で実践できます。今日からでも始められることばかりですので、ぜひ自分のライフスタイルに合った方法を取り入れてみてください。




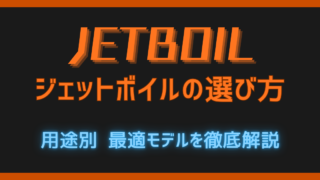





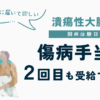


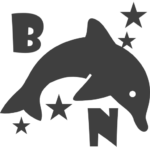

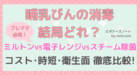



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません